4月2日は、国連の定めた『世界自閉症啓発デー』、4月2日~8日は『発達障害啓発週間』です。
2025.04.02
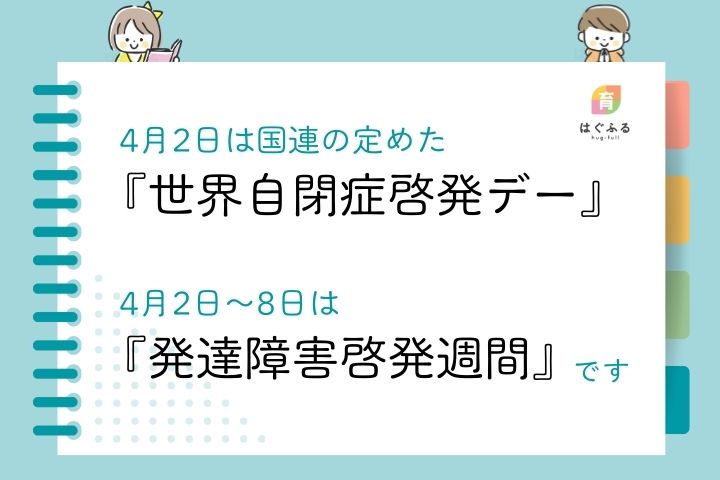
『世界自閉症啓発デー』、『発達障害啓発週間』
毎年4月2日は国連総会が定めた『世界自閉症啓発デー』です。
また、日本でも、発達障がいについて広く啓発するため、4月2日から8日を『発達障害啓発週間』としています。
この期間、自閉症をはじめとする発達障がいについて理解してもらう取組みが世界各地で行われています。
〈参考〉
世界自閉症デー日本実行委員会〈公式サイト〉:https://www.worldautismawarenessday.jp/
発達障害啓発週間:政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/data_room/calendar/202504/event-3226.html
発達障がいとは?
発達障がいとは、生まれながらに脳機能のどこかに障害があることで起こるもので、家族のしつけや、環境によって現れるものではありません。
また、子どもの性格によるものでもなく、考え方を変えれば解決できるものでもありません。
子どもが大人になるまでの間に、必要な発達の段階がありますが、この段階をクリアできない場合(生活面での支障が出る場合)、発達障がいと考えます。
(はぐふる:自閉症の記事より一文を抜粋)
発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの1)が「発達障がい」であるとされています。
1)文部科学省:特別支援教育について:発達障害者支援法(2025年1月閲覧:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1376867.htm)
![]()
発達障がいの一例
・注意欠陥多動性障害(ADHD、注意欠如・多動症)
・学習障害(LD、限局性学習症)
・自閉スペクトラム症(ASD、自閉症)
・発達性協調運動障害(DCD)
・知的障害
・発達性言語障害
・感覚処理障害 など
![]()
自閉症とは?
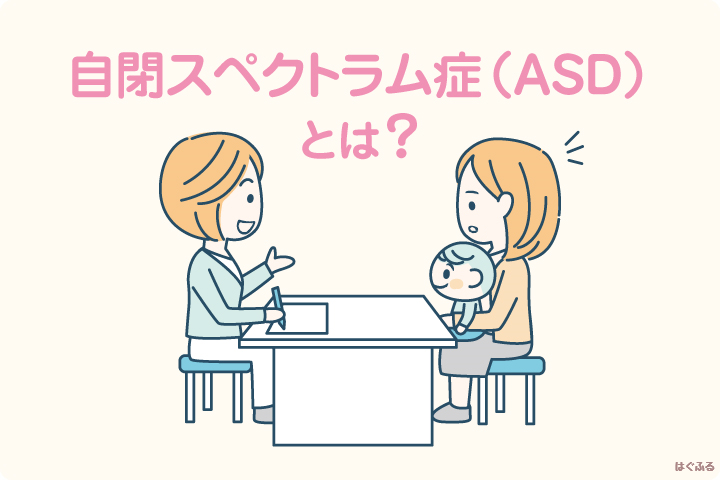
自閉症は、相手の表情、視線、身振りなどから相手の考えていることを推し量ったり、自分の考えていることを伝えたりするのが不得意なほか、こだわりが強いなどの特徴がある障がいです。
以前には、自閉症は、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害などと同じ、広汎性発達障害の1つに分類されていましたが、最近では、それぞれの間に明らかな境界線を引けないことから、対人関係の難しさやこだわりなどの自閉症の特徴を持つ障がい全体を1つのスペクトラム(連続体)と捉えようとする考え方に移ってきています。
ですから、障がいの名前も、自閉スペクトラム症(ASD)や自閉症スペクトラム(AS)と呼ばれることも多くなってきています。
下記の記事より抜粋:▽詳しくはこちらの記事をチェック
療育とは?

発達障がいに関する内容を調べていると、「療育」という言葉が度々出てきます。
発達に気がかり・つまずきを示す子どもを対象に、福祉的・心理的・教育的及び医療的な支援を行う発達支援のことを「療育」といいます。
「療育」はどのような機関で、どのようなことが行われているのかについて、
淑徳大学内に設置された療育機関である、淑徳大学発達臨床研究センターにおうかがいし、同センター長であり、淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 教授の池畑美恵子先生に取材しました。
本日4月2日に、【前編】「発達障害の療育現場」ってどんなところ?療育とは「とても丁寧に子育てをすること」を公開しています。
療育について「とても丁寧に進めていく子育て・保育・教育」と説明してくださった池畑先生の記事をぜひチェックしてみてください。
▽詳しくはこちらの記事をチェック
※後編の記事は4月8日(火)に公開されます。
はぐふるでは、今後も啓発活動を続けて参ります。



 子育ての記事を検索
子育ての記事を検索