【医師監修】乳児湿疹:『 アトピー性皮膚炎 』をわかりやすく解説-子どものかゆみを伴う湿疹
2024.05.22
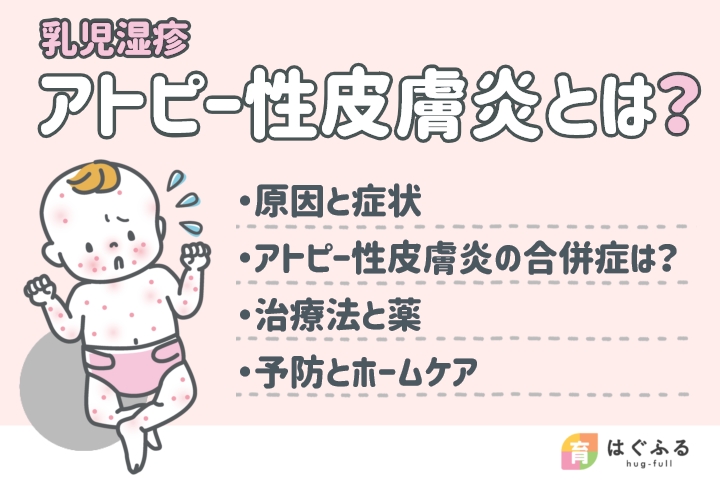
【監修】松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医
1. アトピー性皮膚炎 とはこんな病気
2. アトピー性皮膚炎 の原因は?
3. アトピー性皮膚炎 の症状は?
4. アトピー性皮膚炎 の合併症は?
5. アトピー性皮膚炎 の検査でわかること
6. アトピー性皮膚炎 の治療法と薬
7. アトピー性皮膚炎 のホームケアと予防
1. アトピー性皮膚炎 とはこんな病気
症状別:発疹
体の部位:全身
乳児湿疹(にゅうじしっしん)は、生後1歳前後の子どもにできる皮膚の湿疹(赤み、ぶつぶつなど)をひとまとめにした病気のことです。
その中には、アトピー性皮膚炎、脂漏性湿疹(しろうせいしっしん)などが含まれます1)。
ここではアトピー性皮膚炎について説明します。
脂漏性湿疹は📖こちらの記事で紹介しています。

アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が出て症状が悪くなったり良くなったりを繰り返す皮膚の病気です。
皮膚にもともと備わる「バリア機能」の低下や、アレルギー反応を起こしやすい「アトピー素因(アトピー体質)」などが複合的に関与して発症します。
バリア機能の低下に対するスキンケアや、湿疹を抑える塗り薬などの治療があります。
適切な治療を続けることで、やがて良くなるとされています2) 。
アトピー性皮膚炎は1930年に報告され、ギリシャ語のアトポス(場所が特定されてない、いろんなところに発生する)に由来しているとされています。
2. アトピー性皮膚炎 の原因は?
アトピー性皮膚炎は、アレルギーの素因と環境要因が関連しており、先進国で増加しています。
清潔さを高めると感染症は減少しますが、先進国は衛生的な国が多いため、細菌に暴露する機会が減ります。
そのため、免疫機能が活躍せず、アトピー性皮膚炎の増加と関連しているとされています。
■アレルギー性皮膚炎の要因
3. アトピー性皮膚炎 の症状は?
乳児のアトピー性皮膚炎では、顔(ほお、おでこ)や頭の皮膚が乾燥し、赤みを帯びてきます2)。
そして、ぶつぶつができ、かゆみを伴います。
顔全体、首、背中、脇腹、手足などにも広がります。
病変は左右に現れるのが特徴です。
年齢が上がるにつれて、病変はより限定され、腕と脚、主に膝窩屈曲部と手、下肢、首にのみ現れる傾向があります。
また、季節によって症状が変動します。

アトピー性皮膚炎は、3歳までにおよそ3人に1人が発症するという研究結果があり2) 、この数十年で患者は増加しているとされています2)。
なお、アトピー性皮膚炎のかゆみによって夜十分に眠れないと、子どもの身長の伸びが悪くなったり、学校生活で本来の力を発揮できなくなってしまったりするなど、日常生活に支障をきたすことがあります3) 。
適切な治療を続けることで、いつの間にか湿疹ができなくなったり、軽い乾燥肌だけになったりすることが期待できる病気です。
4. アトピー性皮膚炎 の合併症は?
アトピー性皮膚炎は、他の病気を合併することがあります。
📖気管支ぜんそく、
📖食物アレルギー、
アレルギー性鼻炎、
アレルギー性結膜炎などのアレルギー疾患が代表的です。
📖 子どもはアトピー性皮膚炎があると 食物アレルギー になりやすい?【執筆・監修:アレルギー専門医】
皮膚を引っかいた傷から細菌や真菌が侵入し、細菌感染症になることがあります(ブドウ球菌、伝染性軟属腫、カンジダ感染)。
その場合は、「皮膚が赤く腫れてきて痛む」「水ぶくれのようになる」といった症状が現れます。
より重症の感染症として、カポジ水痘様発疹症(かぽじすいとうようほっしんしょう)というウイルス感染もあります。
小さな水ぶくれが顔と首に「ばらまいたように」できます。
主な原因は単純ヘルペスウイルス(HSV)です。
このウイルスは年齢を問わず、唇の周りの単純疱疹を起こすウイルスですが、乳幼児がHSVに初めて感染した場合にカポジ水痘様発疹症が起こることがあります4) 。
アトピー性皮膚炎の他にも、皮膚の病気がある人に生じやすいとされます。
5. アトピー性皮膚炎 の検査でわかること
アトピー性皮膚炎の検査としては、採血してアレルギーに関わるIgEがどれくらいあるかをみる検査や、皮膚の病変の重症度や勢いを示す項目を測る検査があります。
IgE レベルのモニタリングは、疾患の重症度の日常的な評価にはなりません。
6. アトピー性皮膚炎 の治療法と薬
アトピー性皮膚炎の治療は、
①スキンケア(皮膚の清潔を保ち、うるおいのある状態を保つこと)
②薬物治療(皮膚の炎症〈湿疹〉を抑える治療)
③環境整備(環境中の悪化因子をみつけ、可能な限り取り除くこと)の3つが治療の基本です3) 。
①スキンケア
基本となる治療法として、皮膚のバリア機能低下に対処するためのスキンケアが大切です。補助的に、かゆみ止めの飲み薬が使われることもあります。
保湿剤を使って、皮膚に対する外的な刺激を避け、皮膚を清潔に保ち、皮膚の潤いを保つようにします。湿疹が治った後にもスキンケアを続けることで、皮膚のバリア機能を補正することができます。
![]()
②薬物治療
炎症(湿疹)を抑えるためには、抗炎症作用のあるステロイドの塗り薬や免疫抑制作用のある塗り薬が使われます。
最近では、炎症に関わるヤヌスキナーゼ (JAK)をブロックする新しい薬剤が登場しました。
ステロイド入り塗り薬、保湿薬・皮膚保護薬、抗ヒスタミン薬・免疫抑制薬の塗り薬にどのような種類があるかとその塗り方については、こちらで紹介しています。
📖『 抗ヒスタミン薬 ・免疫抑制薬の塗り薬の効果は?』
📖『 保湿薬 ・皮膚保護薬』子ども(小児)の処方箋
📖『ステロイド入り塗り薬』子ども(小児)の処方箋
皮膚のバリア機能に対するケアと、湿疹を速やかに抑える治療。これらを車の両輪として行い、よい状態を長くキープすることを目指しましょう。
カポジ水痘様発疹症になったときは、抗ウイルス薬の飲み薬や注射薬が使われます。
📖『 抗ウイルス薬 』子ども(小児)の処方
その際、アトピー性皮膚炎の治療をどうするかは、医師と相談しましょう。
![]()
③環境整備
悪化する因子をみつけ、可能な限り取り除くことも重要です。
温熱、発汗、ウール繊維、精神的ストレス、食物、感冒、ダニや室内塵、花粉、ペットの毛など、原因となるものを避け、環境を整えます。
7. アトピー性皮膚炎 のホームケアと予防
💡清潔を保つことと保湿がポイントです。
近年、乳幼児のアトピー性皮膚炎を予防できるかについての研究が進んでいます。
乳児のころから、皮膚を清潔にした上で保湿を続けると、アトピー性皮膚炎の発症リスクを減らすことができるという研究結果があります5) 。
アトピー性皮膚炎の子どもの皮膚では、よだれや涙、飲み物や食べ物が残る、衣類とこすれるなど、外的な刺激が悪化の原因になっている可能性があります。
よだれはこまめに拭き取るのがよいでしょう。
だた、そのときにゴシゴシこするのはやめましょう。軽く当てるようにするのがよいでしょう。
入浴やシャワー浴は、皮膚に付いた汚れ、汗・皮脂などを落とすのに重要です。
きれいになった皮膚に塗るからこそ、薬も本来の効果を発揮できるといえます。
よく泡立てた石けんなどを使って、手のひらで優しく洗いましょう。
すすぎも十分にします。
お風呂やシャワーができない時は、塗れたタオルで拭ってもよいです。

薬は十分な量を塗った方がよいという考え方のもと、フィンガー・チップ・ユニット(FTU)という目安が提唱されています。
大人の人差し指の先端から第一関節まで乗る量の薬を、大人の手のひら2枚分に相当する面積の皮膚に塗るという意味です。
『参考資料』
1) 医学書院医学大辞典.医学書院.2010
2) 日本アレルギー学会、日本皮膚科学会.アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021.
3) 国立成育医療センター.(2024年2月13日閲覧:https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/allergy/atopic_dermatitis.html#section5)
4) 渡辺大輔ほか.日臨皮会誌 33:372-382、2016
5) Kenta Horimukai、et al. J Allergy Clin Immunol. 134:824-830、2014
《 監修 》
-
松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医
神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。
神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。小児科専門医、小児神経専門医。
📖子育てに掲載中の松井潔先生監修記事一覧
休日・夜間の子どもの症状で困った時は【☎♯8000】保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。
この事業は全国統一の短縮番号♯8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。
厚生労働省ホームページ:子ども医療電話相談事業(♯8000)について【本サイトの記事について】
本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.
登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。
また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。



 子育ての記事を検索
子育ての記事を検索